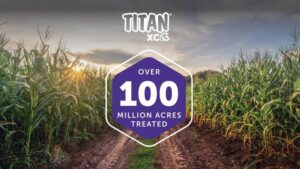【2025年版】アグリテック最前線:スマート農業を牽引する国内スタートアップと導入のポイント
近年、IoT・AI・ロボティクスを活用した「アグリテック(AgriTech)」に取り組むスタートアップが増え、現場の省力化・生産性向上や6次産業化を支える技術が急速に実用化されています。本記事では、アグリテックの概要と市場動向を整理した上で、注目の国内スタートアップを分かりやすく紹介し、農業経営者や導入検討者向けの実践的なアドバイスをお届けします。
出典:株式会社矢野経済研究所「スマート農業市場に関する調査(2024年)」ほか、各社リリースを基に作成
アグリテックとは何か ― スマート農業の定義と狙い
アグリテックは「Agriculture(農業)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、IT・ICT・ロボティクス・バイオ技術などを農業に応用する取り組みを指します。代表的な狙いは以下の通りです。
- 労働力不足の緩和:収穫・散布・選別などの自動化で省力化を実現します。
- 生産性・品質の向上:センサーやAIで最適管理を行い、収量や品質を安定させます。
- サプライチェーン効率化:栽培から出荷・流通までをデータでつなぎ、ロス削減や販売最適化を図ります。
「スマート農業」とも呼ばれ、単なる機械化に留まらず、データとアルゴリズムに基づく“高度な営農支援”へと進化しています。
市場規模と成長見通し
矢野経済研究所の調査によると、2023年度の国内スマート農業市場規模は約375億円で、農機の自動化(自動操舵トラクター、ドローン、ロボット農機)や営農支援ソリューション(農業クラウド、環境制御装置)が成長をリードしています。センシング・AIの高度化や無人化の進展を背景に、2029年度には約700億円規模に達する見通しです。
市場拡大は技術の成熟と導入事例の蓄積に依存しており、地方自治体・JA・大手事業者との連携が普及の鍵となります。
注目の国内スタートアップ(2025年最新)
ここでは、現場導入や事業化で注目されているスタートアップをピックアップし、それぞれの強みと現場への示唆を解説します。
スパイスキューブ株式会社
都市部の居抜き物件を活用した小規模植物工場を設計・開発し、LED照明+養液栽培によるプラント導入から栽培指導、流通までを一気通貫で支援します。商業施設での実証(大阪のATCなど)を通じて、都市型生産と消費者体験を組み合わせたビジネスモデルを実装している点が特長です。
AGRIST株式会社
AI搭載の自動収穫ロボットを中核に、衛星データや現場データを融合した農業DXを推進します。大手向けコンサルティングやスマート農業研修を提供し、耕作放棄地活用や人材育成の支援にも注力している点が現場導入で評価されています。
株式会社ミライ菜園
AIによる病害虫予測アプリ「TENRYO」と診断SNS「SCIBAI」を提供。独自の病害虫発生履歴データに気象解析を組み合わせ、最大7日先のリスク予測を実現しています。JA導入事例では収量改善の実績も出ており、予防的防除と資材コスト低減に貢献しています。
株式会社オプティム
ドローンを用いたピンポイント農薬散布技術を世界で初めて実用化した企業です。AI解析で発生箇所を特定し、農薬散布の最適化によって薬剤使用量と労働時間を大幅に削減。実運用面積は累計で2万6,000haを超え、精密防除の普及に寄与しています。
クレバアグリ株式会社
温湿度やCO₂、土壌水分・ECなど多様なセンサーを設置してデータ収集を行い、AIで生育シナリオや経営計画まで導出する総合的な営農支援プラットフォームを提供します。GAP対応や財務管理まで含めた経営支援が強みです。
inaho株式会社
自律型収穫ロボットを開発し、収穫適期の判断までAIが担うことで熟練技術を補完します。欧州でのトマト収穫ロボット実証など海外展開も進めており、品質維持と省力化を同時に実現するソリューションが注目されています。
株式会社セラク(みどりクラウド)
ハウス環境を2分間隔で自動収集し、スマホやWebで「見える化」するサービスを提供。出荷業務のDX化機能を導入した事例では、伝票・検品作業時間が約77%削減されるなど、流通工程まで含めた効率化効果が実証されています。
メビオール株式会社(アイメック®)
医療用膜技術を転用したナノサイズ多孔質ハイドロゲルフィルム農法「アイメック®」を開発。高糖度野菜の高付加価値化に成功しており、従来農法の何倍もの価格で取引される事例もあります。付加価値戦略を追求する農家に対して有効な技術です。
株式会社アグリゲート
生産から流通・小売までを垂直統合する「SPFモデル」を展開し、都市型青果店の運営やオンライン連携でフードロス削減と仕入強化を進めています。大手との資本提携によりリソース共有を進め、スケールメリットを生かした流通改革を推進しています。
サグリ株式会社、HarvestX株式会社 ほか
サグリはAIと衛星リモートセンシングで耕作放棄地や農地の活用状況を解析し、自治体との連携で復興・営農再開支援を行っています。HarvestXは植物工場向けの無人授粉・収穫ロボットを開発し、国のスタートアップ支援プログラムに選出されるなど国際展開も視野に入れています。
導入・投資を検討する際のチェックポイント
多様なソリューションの中から現場に合った技術を選ぶために、以下の観点で評価することをおすすめします。
- 課題の切り分け:省力化・品質向上・出荷効率化のどれを優先するかを明確にします。
- ROIの見積もり:初期投資、ランニングコスト、人件費削減効果を数値で比較します。
- インターペラビリティ:既存機器や管理システムとの連携性、データフォーマットの互換性を確認します。
- 運用体制と保守:現場のITスキル、保守サポートの有無、故障時の対応体制を評価します。
- データの利活用と所有権:取得データの権利関係や活用方針を明確にしておくことが重要です。
- 実証(PoC)から段階導入:小規模での実証→評価→スケールという段階を踏むことでリスクを抑えられます。
導入後に期待できる効果と現実的な課題
期待できる効果は、省力化・作業時間短縮、薬剤や肥料の適正化によるコスト削減、収量・品質の安定化、流通工程の効率化など多岐にわたります。一方で現実的な課題も存在します。
- 初期投資と回収期間の長さ:機器やシステムの導入コストは無視できません。
- 人材育成の必要性:デバイスやソフトの運用・解析を担う人材が必要です。
- 現場条件の多様性:気候や品目、圃場条件によって効果に差が出る可能性があります。
- 制度・規制対応:ドローン運用や農薬散布の規制に適合させる必要があります。
これらを踏まえ、補助金や共同出資、共同実証などでリスク分散を図ることが有効です。
ターゲット別の短期アクションプラン
読者層ごとに取るべき短期アクションを整理します。
- 農業経営者・現場農家:まずは現状のボトルネック(収穫作業、人手、品質ばらつき)を特定し、PoCで費用対効果を検証します。
- 農業法人の経営企画:中長期のIT投資計画にアグリテックを組み込み、ROIシミュレーションと運用体制の整備を行います。
- 農機・資材メーカー:既存製品のIoT化や他社サービスとのAPI連携を強化し、ソリューション提供力を高めます。
- AgTechスタートアップ:現場への導入実績を優先的に積み、自治体・JA・大手との協業でスケールする戦略を推奨します。
- 自治体・JAの営農支援担当:地域の営農課題に応じた技術マッチングや補助金・実証支援を拡充します。
- 投資家・支援機関:技術の実用性・事業モデルのスケーラビリティとともに、現場での受容性を重視して評価します。
まとめ:技術だけでなく「現場適合性」が普及の鍵
2025年時点でアグリテックは確実に現場実装のフェーズに入っており、市場は今後も拡大が見込まれます。しかし、真に農業の生産性や収益性を高めるためには、技術の先進性だけでなく「現場適合性(現場で使い続けられるか)」が重要です。小さな実証から始め、得られたデータを通じて運用を改善し、周辺事業者や行政と連携することで、持続可能な導入が可能になります。
本稿で紹介した各社の取り組みは、多様な現場課題に対するヒントになります。導入を検討する際は、自身の営農課題の優先順位を明確にした上で、まずは小さな実証を通じて効果を検証することをおすすめします。
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
【2025年】農業のスタートアップ企業を紹介!スマート農業・アグリテックの最前線とは
https://minorasu.basf.co.jp/80286