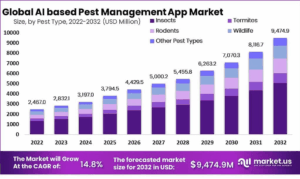融資支援で増える中国製ドローン依存──「K農機近代化」の実態と今、農現場が備えるべきこと
韓国で今年実施された農業用ドローンの購入向け融資支援の約9割が中国製ドローンに向けられていることが、国会議員の資料分析で明らかになりました。政府が掲げる「農機近代化」政策の下で、購入支援は拡大する一方、国産機の普及や開発支援は遅れており、現場とサプライチェーンに潜むリスクが顕在化しています。農機のスマート化を進める国内の営農法人やメーカー、自治体の技術担当者にとっても他山の石となる事例です。この記事では事実関係を整理し、現場が取るべき対策をわかりやすく解説します。
現状のポイント(数字で見る実態)
- 今年1〜8月の農業用ドローン向け融資支援額は合計47億7,100万ウォン。そのうち中国製の購入向け融資は43億2,900万ウォンで、割合は90.7%に達しています。
- 今年の融資で購入されたドローン台数は中国製が257台、国産が34台でした。
- 過去5年(2021〜2025年8月)累計では、政府融資で購入された農業用ドローン1,235台のうち中国製は1,030台で約83%、融資支援額でも中国製が177億2,200万ウォン(全体の88.2%)を占めています。
- 中国製ドローンへの融資額は年々増加傾向で、2020年の約9億ウォンから2023年は約34億1,800万ウォン、昨年は約47億7,000万ウォンへと拡大しています。一方、国産ドローン向けの融資額は2021年の4億9,600万ウォンから昨年は3億8,400万ウォンへと減少しています(約22.5%減)。
なぜ中国製が多いのか──要因整理
政府側は「ドローン市場全体で中国製の占有率が高いため」と説明しています。実際、価格競争力、量産体制、部品供給の確保、販売・サポート網の広さなどで中国メーカーが優位に立つ場面が多く、補助や融資によって初期導入コストが下がると選択が中国製に傾きやすい構図です。
潜在リスク:サプライチェーンと安全保障
しかし、依存度の高さは明確なリスクを伴います。既に中国政府は2023年以降、「軍事安保」を理由に高性能ドローンや主要部品の輸出規制を強化しています。2024年7月には赤外線カメラ、レーダー、通信装置などの一部主要部品に対する規制が強化されており、将来的に部品供給が止まれば運用・保守に深刻な影響が出る恐れがあります。
農現場と自治体、メーカーが取るべき現実的な対策
単に「国産を応援すべき」というだけでなく、現場レベルで実行できる具体策が必要です。以下は営農法人、個人農家、農機メーカーや自治体の技術担当者向けの実務的な提案です。
営農法人・個人農家(導入現場)
- 購入前にサプライチェーンを確認する:主要部品(プロペラ、モーター、送受信モジュール、カメラなど)の供給元と代替手段、在庫保有の有無を確認します。
- 保守・修理体制の確認:国内で修理や部品交換が可能か、現地代理店の対応力、ソフトウェア更新の可否をチェックします。
- リスク分散の検討:重要作業用の機体は複数ブランドで分散保有するか、代替作業(有人散布や共同利用)計画を用意します。
- 契約条件を見直す:ファームウェアの恒久的なアクセス、OTA更新の保証、長期延長保証などを交渉材料にします。
農機メーカー・部品供給業者
- 国内生産・組立の強化:完全自前でなくても「国内組立+非規制部品」の組み合わせで供給安定性を高めます。
- オープンなソフトウェア・ハードウェア基盤の採用:互換性の高い標準規格を採用して部品の選択肢を広げます。
- 代替部材の開発と在庫戦略:規制対象になりやすい高機能部品の代替設計や国内部品調達ルートの確立を進めます。
自治体・政府(支援・政策面)
- 融資・補助の条件にサプライチェーン健全性評価を導入する:短期的な価格優先ではなく、長期的な保守・調達リスクを評価基準に組み込みます。
- 国産R&D支援の拡充:コア部品(カメラ、通信、センシング)に対する研究開発補助と試作支援を強化します。
- プロトタイプの現場試験と共同調達:自治体単位での共同購入や実証事業を通じ、国産機の実利用データを蓄積します。
- 認証や品質基準の整備:農業用途に求められる安全・耐久・保守性の基準を明確化し、国内製品の競争力を高めます。
なぜ今、日本の農業者も注目すべきか
今回の韓国の事例は、補助や融資が短期的に導入を促進する反面、長期的な国産育成や供給安定策を伴わないと依存が進むことを示しています。日本でも価格や導入補助を優先するあまり、海外依存が深まれば同様のリスクが生じます。国内の営農法人や自治体は、導入判断において単なる機材コストだけでなく、部品調達リスク、保守体制、長期的な運用コストを重視する必要があります。
まとめ:導入加速と同時に「供給の強靭化」を
ドローンはスマート農業の中核技術であり、その普及は農作業の効率化に直結します。一方で、中国製の安価で高性能な製品に頼り切ると、輸出規制や供給断絶の影響を受けやすくなります。政府の融資や補助は導入を後押ししますが、同時に国産技術の育成やサプライチェーンの多様化を政策的にサポートすることが重要です。営農現場、メーカー、自治体がそれぞれの立場でリスクを見極め、短期導入と長期安定供給の両立を図ることが求められます。
(参考:国会議員提出資料および東亜日報報道を基に要旨を整理)
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
農食品部の「K農機近代化」支援、実態は融資購入ドローンの8割が中国製 | 東亜日報
https://www.donga.com/jp/article/all/20251010/5892451/1