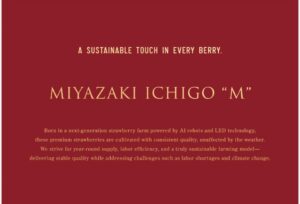鳥獣害対策ドローン「BB102(Bird&Beast102)」が商品化——県の実証支援で実用化に前進
県が推進する「ドローン実証実験プロジェクト」の支援を受けて開発された鳥獣害対策ドローンが、このたび商品化されました。製品名は「BB102(Bird&Beast102)」。設計・製造を行うのは株式会社NTT e-DroneTechnologyで、県の実証実験で得られた知見を活かして実用化に結びついた製品です。営農法人や集落営農、個人農家の現場責任者、農機メーカーや自治体の技術担当者に向けて、本製品の特徴と導入時のポイントをわかりやすく解説します。
製品の概要(主な仕様と特徴)
- 製品名:BB102(Bird&Beast102)
- 開発・製造:株式会社NTT e-DroneTechnology(国内拠点での設計・製造)
- 主な機能:動物の忌避を促すレーザー照射機を搭載。ハト、カラス、ムクドリ、シカなどが苦手とする波長のレーザー光を発射して追い払いを行います。
- 稼働時間:リチウム電池で最大約7時間の照射が可能(連続運用時間の目安)。
- 価格:330万円(税込)※講習受講費1名分(初心者)を含む
- 画像提供:株式会社NTT e-DroneTechnology
県の支援内容と商品化までの経緯
県はドローンの社会受容性向上と実用化の促進を目的に、全国から有望なプロジェクトを公募し、開発から実証までの総合支援を実施しました。本製品については、産業用ドローンに鳥獣追い払い装置を搭載し、遠距離・広範囲の追い払い業務においてどのような効果が得られるか、業務効率化の度合いはどうかを現場で検証する実証実験が行われました。実証で得られた知見が商品設計や運用ノウハウに反映されています。
現場で期待できる効果
- 広範囲を短時間でカバーできるため、人手による巡回や音声・光・ネット設備のみの対策に比べて効率的な追い払いが期待できます。
- 高密度の集落営農や平地の大面積圃場、畜産施設周辺などでの定期的な追い払いに向いています。
- ドローンによる非接触での追い払いは、夜間や人が入りにくい場所での作業負担を軽減します(ただし夜間飛行の許可等のルール遵守が必要です)。
導入前に押さえておくべきポイント(注意点)
- 安全性と法令:レーザー光の使用は目に対する安全性に配慮する必要があります。製品の安全基準(レーザークラス)や取扱い説明書に従い、周囲住民や作業者の安全確保を徹底してください。また、ドローンの飛行は航空法や地方自治体の条例、夜間飛行規制、飛行禁止区域等の制約がありますので、事前に許可・確認が必要です。
- 生態への影響:忌避効果は種や個体群によって差があります。継続した単一手法だけでは習性により効果が薄れる場合があるため、複数の対策(ネット、柵、圃場管理など)との併用が重要です。
- 気象条件:強風・降雨時は飛行制限や追い払い機能の効果低下が想定されます。運用スケジュールは天候に応じて柔軟に調整してください。
- 運用コストとメンテナンス:初期投資は高額(330万円)ですが、稼働回数や効果の割にコスト削減効果があるかどうかは業態や被害状況によって異なります。バッテリー管理や点検、法定整備の考慮が必要です。
導入プロセスのおすすめ実践プラン
- 現状把握:導入対象の被害状況(被害頻度、面積、被害額)と優先対処箇所を明確化します。
- 小規模試行:まずは1〜2回のトライアルフライトで効果を計測します。期間中の被害発生件数や農作物の品質・収量を記録して比較してください。
- 指標設定:効果測定の指標として「被害件数の減少率」「作業時間削減」「追い払いに必要な人員削減」などを設定します。
- 運用ルール化:飛行スケジュール、操縦者の資格・講習受講(含まれる1名分の講習を活用)、安全対策の手順を文書化します。
- スケールアップ:効果が確認できれば、導入面積を拡大したり、自治体や近隣営農者と共同で運用するモデルも検討します。
費用対効果の考え方(着目すべき数値)
- 初期投資:330万円(講習1名分含む)
- ランニングコスト:バッテリー交換、消耗品、整備費、操縦者の追加講習費などを見積もる必要があります。
- ベネフィット指標:被害額の削減、作業人件費の削減、収量・品質改善に伴う増収を定量化して、回収期間(投資回収期間)を試算してください。
- 共同利用モデル:営農法人・集落・自治体で共同購入・運用することで、1事業者あたりの負担を下げることが有効です。
導入後の運用・連携のポイント
- データ蓄積:フライトログや照射履歴、被害発生データを保存し、時間経過での効果や最適運用パターンを分析してください。将来的にはAIを活用した最適ルート生成や効果予測に結びつけることも可能です。
- 周辺連携:自治体や近隣農家、猟友会などと連携して、地域ぐるみの対策を打つと効果が持続しやすくなります。
- 教育・研修:操縦技術だけでなく、レーザーの取り扱いや生態への配慮に関する研修を定期的に実施することをおすすめします。
問い合わせ先(購入・導入相談)
製品に関する問い合わせや導入相談は、下記へご連絡ください。
株式会社NTT e-DroneTechnology
住所:埼玉県朝霞市北原2-4-23
担当:サービス推進部 普及部門 和田
メール:agri@nttedt.co.jp
電話:048-485-8335
県への問い合わせ(実証支援に関する窓口)
本製品の実証支援に関する情報や、県内での連携・導入支援については県の窓口へお問い合わせください。
神奈川県産業労働局産業部産業振興課
課長:髙橋 電話 045-210-5630
技術開発グループ:本田 電話 045-210-5640
まとめ — 現場での導入を検討する際の一言アドバイス
BB102は、広範囲・遠距離の追い払いを無人で実施できる点が大きな強みです。一方でレーザーの安全管理やドローン飛行に関する規制対応、継続的な効果を確保するための運用設計が不可欠です。まずは小規模な実証導入で効果を検証し、自治体や近隣と連携した運用モデルを模索することをおすすめします。実証で得られたノウハウは、他の営農現場でも再現可能な形に整理できるため、業務効率化と被害低減の両立を目指す現場にとって有力な選択肢となるでしょう。
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
鳥獣害被害対策ドローンが商品化されました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001261.000108051.html