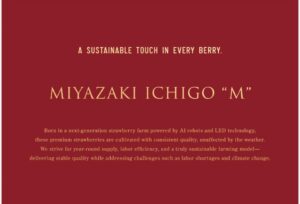鳥獣害対策ドローン「BB102」提供開始──レーザーで高所もカバー、自動航行で現場負担を軽減
発表:株式会社NTT e-Drone Technology(代表取締役社長:滝澤 正宏)/提供開始日:2025年10月1日(水)
全国で深刻化するイノシシ・シカ・カラスなどの鳥獣害対策に、新たな選択肢が登場しました。NTTイードローンは2025年10月1日より、鳥獣害対策専用ドローン「BB102」の提供を開始します。BB102は国内で初めてレーザーを搭載した鳥獣害対策ドローンとして開発され、高い忌避効果と自動航行機能により、農作物被害の抑制と現場の負担軽減を両立することを目指しています。
開発の背景と狙い
農林水産省の推計によれば、鳥獣害による農作物被害は年間で約200億円規模にのぼり、地域農業や畜産への影響は深刻です。加えて、鳥インフルエンザなどの防疫上の課題もあり、人手と時間をかけた対策が求められています。NTTイードローンはこれまでの農業用ドローンの知見を活かし、非致死的で持続可能な対策手段としてBB102を開発しました。
BB102の主な特徴
- レーザー搭載(国内初)による視覚的な忌避効果で、広範囲の鳥獣の追い払いを狙います。屋上や高所など、地上設置型の装置では対処が難しかった領域にも対応可能です。
- 自動航行機能を備え、事前設定したコースやスケジュールに基づく巡回運用が可能です。定期巡回で人的負担を軽減します。
- 農作物への被害抑制と、鳥獣害対策業務に要する人的・時間的コストの削減を意図しています。
- 非致死的な対策であり、地域や生態系に対する配慮を重視した設計です。
導入時に確認しておきたいポイント(現場向け実務チェック)
BB102は魅力的な選択肢ですが、実運用にあたっては以下の点を事前に確認・準備することをおすすめします。
- 安全性と規制の確認:レーザー照射や無人航空機の運用は、航空法や各種安全基準、地元自治体のルールに関わります。具体的な運用ルールや許可申請については、NTTイードローンと調整するとともに関係当局へ確認してください。
- 運用計画と時間帯:動物の行動パターンに合わせた巡回スケジュール設定が効果を左右します。夜間運用や低照度環境での性能についても確認が必要です。
- 効果の違い:レーザーによる忌避は鳥類に高い効果が期待されますが、イノシシやシカなど哺乳類への反応は個体や状況で差が出ることがあります。複合的な対策(フェンス・音響・捕獲等)との併用を検討してください。
- 運用コストと保守:機体の稼働時間、バッテリー交換、点検・修理体制、操縦者(運航管理者)や現地担当者の教育・研修費用を含めたトータルコストを見積もってください。
- データ連携と記録:自動航行ログや映像記録を防護計画や被害記録として活用すると、効果検証や補助金申請時に役立ちます。管理ソフトとの連携についても確認しましょう。
現場での運用シナリオ例
- 圃場周囲の定期巡回:日没後・夜明け前に設定したルートを自動巡回し、営農時間外の侵入抑止を図ります。
- 高所や屋根上のポイント対策:倉庫屋上や施設の高所に止まる鳥類対策として、地上設置器具が届きにくい場所にも対応します。
- 被害発生時の迅速対応:畑で被害が確認された際に即時飛行させて追い払い、被害拡大を抑える運用です。
- 防疫対応の補助:家畜施設周辺での鳥類対策により、飛来リスクを低減し防疫対策を支援します(ただし、防疫措置は自治体や獣医師の指示に基づいて実施する必要があります)。
導入を検討する上での質問リスト(メーカーに確認すべき点)
導入検討時にNTTイードローンへ確認すると良い項目の例です。
- 1回の飛行でカバーできる面積と飛行時間、充放電のサイクル性能
- レーザーの照射範囲と安全基準、目や皮膚への影響を避けるための対策
- 障害物検知・衝突回避機能、悪天候時の運用制限
- 自動航行の設定方法、複数地点のスケジューリング機能
- 導入後の保守契約、修理対応、部品供給体制
- 操縦者・運航管理者向けの研修プログラムと費用
- 自治体・関係省庁への届け出や許認可に関するサポートの有無
導入スケジュールとイベント情報
BB102の提供開始は2025年10月1日(水)です。価格はオープン価格となっており、デモ飛行や説明会、意見交換会などの要望にも対応すると発表されています。導入を検討している営農法人や自治体、農機メーカーの技術担当者は実機に触れるよい機会です。
なお、同日より開催される「第15回農業WEEK」(会期:10月1日〜3日、会場:幕張メッセ/千葉県)にて、NTTグループブースでBB102が展示されます。実機のデモや担当者からの説明を直接受けることができるため、現場の具体的な運用イメージを掴む良い機会になります。
最後に──現場目線での期待と注意点
BB102は、レーザー忌避と自動航行を組み合わせることで、これまで手薄だった高所対策や巡回運用の省力化に期待が持てます。特に営農法人や集落営農のように広域を管理する組織にとって、人的負担の軽減は大きなメリットになります。
ただし、完全な「万能薬」ではありません。動物の種類や個体差、環境条件により効果は変動しますし、安全性・法令順守が最優先です。導入前には現地調査、関係者との調整、そして効果検証の計画を立てることをおすすめします。NTTイードローンの説明会やデモを活用して、実運用をイメージしながら自分たちの防除計画にどう組み込むかを検討してください。
(数値データの出典:農林水産省ホームページ)
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
鳥獣害対策ドローン「BB102」の提供開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000142334.html