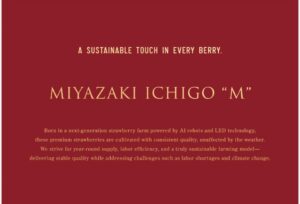農業AIエージェントサービス「V-farmers®」がタマネギで実証開始へ——秋田・大潟村で1年間の現地検証
株式会社日本総合研究所、株式会社JSOL、株式会社みらい共創ファーム秋田(MKFA)は、農業向けAIエージェントサービス「V-farmers®」のプロトタイプを用いた実証実験を、2025年9月25日から2026年9月30日まで秋田県大潟村で実施します。対象は秋播きタマネギで、栽培支援と経営管理支援の有効性、並びに生成AIの精度や既存スマート農機との連携可能性を検証します。
なぜ今、AIエージェントが求められているのか
日本の農業は就業者の急減と高齢化に直面しています。2023年の農業就業者数は約181万人で、1999年から約119万人減少しており、2024年時点の基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳に達しています。この状況は生産の維持やノウハウの継承に深刻な影響を与えています。
こうした課題に対し、V-farmers®は「知見のデジタル化」と「業務の自動化」で支援することで、少人数での大規模営農や新規就農者の早期戦力化、地域における品目転換(例:東北でのタマネギ本格生産)を後押しすることが期待されています。
実証の概要(いつ・どこで・何を検証するか)
- 実証期間:2025年9月25日〜2026年9月30日(準備は2025年6月から開始)
- 実証サイト:みらい共創ファーム秋田(秋田県南秋田郡大潟村)— 経営面積65ヘクタール、実証対象6ヘクタール
- 対象作物:タマネギ(秋播きを主対象、想定スケジュール:8月播種、10月定植、翌年6〜7月収穫)
- 検証項目:
- 経営管理支援サービスの有効性(作業計画、在庫・出荷管理、売上の可視化など)
- 栽培支援サービスの有効性(作業マニュアルの提示、病害リスク分析、栽培ノウハウ補完)
- 農業用生成AIの精度検証(内閣府BRIDGEの枠組みで開発中の農業生成AIを活用)
- スマート農機等との連携検討(API連携による稼働管理など)
- 役割分担:日本総研=ニーズ分析・政策提言・情報発信、JSOL=アプリ企画・開発・運用、MKFA=現場試験導入とフィードバック提供
V-farmers®の主な機能と現場で期待される効果
V-farmers®は栽培データ、気象・土壌センサ、作業日誌、出荷データなどを統合し、農業経営と生産を横断的に支援するAIエージェントです。主機能と期待効果は以下の通りです。
-
作業スケジュール調整(AIによる自動化)
過去データと気象予報、病害リスクを踏まえて作業計画を自動作成・更新します。雨予報に応じた前倒し指示や機具・人員配分の最適化によって、自治体や営農法人の業務負荷を低減できます。 -
作業マニュアル管理・栽培ナレッジのデジタル化
ベテランのノウハウをデジタル化してチャット形式で参照可能にすることで、新規就農者や外国人パートタイマーの早期戦力化を支援します。マニュアルは現場の作業データにより随時更新されます。 -
出荷管理(OCRなどによる業務効率化)
手書き伝票のOCRで出荷データを自動化し、入金管理まで一貫して可視化します。出荷〜売上確定の流れを短縮でき、経営判断の迅速化に寄与します。 -
多言語対応と現場コミュニケーション支援
日本語のほかインドネシア語、英語、ベトナム語などに対応予定で、現場での人材活用幅を広げます。 -
将来的なAPI連携によるスマート農機との統合
農機の稼働管理やIoTデータと連携することで、より高度な自動化とトレーサビリティを実現できます。
現場で導入する際のポイントと注意点
AI導入で効果を出すためには技術以外の準備も重要です。現場で注意すべき点を整理します。
- データ整備:過去の作業記録、土壌・気象データ、出荷実績のデジタル化が前提になります。データ品質がAIの精度に直結します。
- 通信インフラ:農地によっては通信が不安定な場所があるため、現地での通信環境確認とオフライン運用の仕組みが必要です。
- 操作性と現場適応:作業者がすぐに使えるUI設計、現場での手順見直し、言語対応の精度確認が重要です。
- AIの精度と責任範囲:生成AIや診断結果は参考情報として活用し、最終判断は担当者が行う運用ルールの整備が必要です。
- コストと効果検証:導入コストに対し、労働生産性や作業時間削減、収量・品質向上で投資回収できるかを事前に試算します。
- データ管理・権利:収集データの利用範囲や第三者提供のルール、セキュリティ対策を明確にしておくことが重要です。
導入検討者向けチェックリスト(すぐに使える)
- 試験区画を1〜2ヘクタール程度で設定し、段階的に拡大する
- 測定すべきKPIを決める(作業時間削減率、機械稼働率、収量・歩留まり、伝票処理工数など)
- 現場の代表者とIT担当の窓口を明確にし、定期的にフィードバック会議を行う
- スマート農機や既存の営農支援システムとの接続要件を整理する(API、データ形式)
- 労務面では多言語マニュアルを優先的に整備し、短期雇用者の作業ミス低減を狙う
- 導入前後でのベースライン測定(作業時間、出荷リードタイムなど)を確実に取る
今後の展望と地域・政策への示唆
本実証はタマネギを対象にしていますが、得られた知見は稲作などほか品目への横展開が想定されています。特に東北地域での品目多様化(端境期の解消)や、新規就農者支援、気候変動への適応策として有益な成果が期待できます。
また、国のBRIDGEプログラムや農林水産省のAI農業社会実装プロジェクトと連携することで、現場での実用性検証を基にした政策提言が可能になります。営農法人や自治体にとっては、実証結果を踏まえた導入支援や補助制度の設計が次の課題となるでしょう。
まとめ
V-farmers®の秋田での実証は、農業現場のノウハウ継承と業務効率化を同時に追求する試みです。短期的には作業負荷の軽減や出荷業務の効率化が期待でき、中長期的には若手育成や営農のスケール化、地域の生産安定化に寄与する可能性があります。一方で、データ品質や通信環境、AIの精度と運用ルールといった現場課題の克服が不可欠です。導入を検討する営農法人や自治体は、小さなスケールからの段階的導入と明確なKPI設定、現場の声を反映した運用設計を優先することをおすすめします。
本実証の結果は、2026年以降のスマート農業導入計画や政策議論において注目の指標になると考えられます。実証の進捗や成果は今後も注視していきたいところです。
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
農業AIエージェントサービス「V-farmers®」実証開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000007779.html