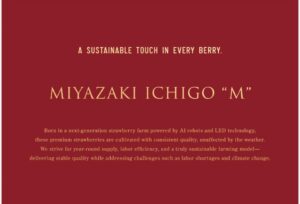ノウタスが「AIぶどう栽培」特許出願を完了、果樹工場モデルで本格展開へ
2025年9月21日、ノウタス株式会社(東京都港区、代表取締役会長:高橋明久)は、自社開発の「AIぶどう栽培システム」について検証を終え、特許出願を完了したと発表しました。企業は「いつでも・どこでも・だれでも」果樹栽培を可能にする、いわゆる「果樹工場」モデルの本格展開を目指しています。本稿では技術の中身、期待される効果、実運用での課題や導入のポイントをわかりやすく解説します。
技術の概要 — ポット栽培×AI×環境制御で栽培サイクルを設計
ノウタスのシステムは複数の要素を組み合わせ、ぶどうの収穫タイミングや周年生産を自在に設計することを目標としています。主な構成要素は次の通りです。
- ポット栽培による根域制限と低温貯蔵での人工休眠による収穫サイクル設計
- 鉢(ポット)単位で栽培房数を制限し、変数を最小化する栽培設計
- 定点カメラや各種センサー(温度・湿度・照度・土壌水分など)からのデータをAIが解析
- 解析結果に基づく水・光・温度・湿度の自動制御で最適環境を提供
期待される効果 — 高付加価値化と作業簡素化
同社はこのシステムによって、以下のような効果を訴求しています。
- オフシーズン供給による高単価化・高収益化(需給優位を獲得)
- 病害発生リスクの低減と農薬使用量の削減
- 作業の自動化・簡素化により「誰でもできる」栽培プロセスの実現
- 遊休施設や空き家を活用した都市型果樹工場の実現による立地多様化
研究連携と品種開発 — 科学とテクノロジーの融合
ノウタスは九州大学、桐蔭横浜大学、AGRIST社などと連携し、培養土の活用や再生可能エネルギー利用、AIロボット収穫など多角的に研究を進めています。さらに林ぶどう研究所と共同で進める新品種「パープルM」など、栽培しやすく魅力的な品種づくりも進行中です。AIによる環境制御と品種設計を組み合わせることで、栽培の再現性と付加価値を高めようとしています。
ビジネス展開と社会的意義
同社は今後の展開として、自治体との遊休施設活用、福祉施設との共同事業による雇用創出、そして「果樹版植物工場」のモデル輸出を掲げ、3年後のグローバル市場進出を目標にしています。気候変動による天候リスクの増大や食料安全保障の観点から、安定的な周年供給や都市型生産の社会的意義は大きいと評価できます。
特許出願の意味 — 知財と事業優位性
特許出願は技術のコア部分に対する権利化の一歩であり、事業化・海外展開を見据える上で重要な戦略です。特にセンサーとAI制御の組合せや、ポット栽培によるサイクル設計のノウハウが保護されれば、競合参入のハードルが上がります。一方で、植物工場分野はプロトコルや運用ノウハウ、データ蓄積が競争の鍵となるため、特許だけでなく運用データとサプライチェーンの確保も重要になります。
導入時に検討すべきポイントと課題
導入を検討する事業者や自治体が押さえておくべき点は次の通りです。
- 初期投資とランニングコスト:環境制御機器、センサー、カメラ、ソフトウェア、エネルギーコストが主要な項目です。特に電力コスト削減策(再生可能エネルギー併設や蓄電)を検討する必要があります。
- スケールメリットと収益性:小規模と中大規模で採算ラインが異なるため、モデルプラントでのパイロット検証を推奨します。
- データ管理とプライバシー:AIの学習データは価値資産です。データの収集、所有権、外部提供のルール整備が必要です。
- 労働と運用体制:自動化で人手は減る一方、運用監視や機器保守のスキルが必要です。地域の雇用創出や福祉連携との整合も重要になります。
- 適合品種の選定:品種によって最適環境や経済性が大きく変わります。既存品種の適応検証や、同社が進める新品種とのセット導入を検討する価値があります。
- 規制・補助金の活用:施設園芸やスマート農業関連の補助金、自治体の遊休施設利活用支援などを積極的に活用することで導入ハードルを下げられます。
導入に向けた実務的な提案
現場管理者や自治体担当者、投資家向けに具体的な導入ステップを提案します。
- パイロットプロジェクトの実施:まずは小規模なモデル導入で生産性・品質・コストを検証します。
- 自治体・福祉施設との連携:遊休施設を活用することで立地コストを抑え、社会的インパクトを高めます。
- 再生可能エネルギーの併設検討:電力使用を最適化してランニングコストとカーボンフットプリントを低減します。
- データ共有と共同研究:大学・研究機関と協働し、気候変動下での栽培最適化を進めます。
- ビジネスモデルの多角化:生果供給だけでなく、体験(アグリテインメント)や人材育成(アグリキャリア)を組み合わせた収益構造を構築します。
投資家・自治体・開発者への示唆
この種の果樹工場モデルは、技術的な独自性と運用データの蓄積で価値を生むため、長期的視点での投資が求められます。自治体は地域の遊休資産を活用した新たな産業創出や雇用創出の機会として、事業者側は運用ノウハウ・品種戦略・エネルギー計画をセットで検討することが重要です。アグリテック開発者にとっては、センサー・AI・ロボットの連携領域での共同開発や標準化がビジネスチャンスになります。
代表コメント
ノウタス代表取締役会長 高橋明久:「私たちは“Win-WinよりFun-Fun”を掲げ、農業をもっと身近で楽しいものに変えたいと考えています。AIぶどう栽培は、『いつでも』『どこでも』『だれでも』関われる農業を目指し、食の未来を支える技術です。ぶどうで日本発の農業イノベーションを世界に届けます。」
まとめ — 実装フェーズに入ったテクノロジー、現場適用が鍵
ノウタスの「AIぶどう栽培」は、特許出願を経て事業化フェーズに踏み出しました。技術自体はポット栽培や環境制御といった既存要素の組み合わせですが、AIによる最適制御と品種改良の組合せが差別化要因になります。導入の鍵は初期コストやエネルギー効率、そして現場の運用ノウハウの蓄積です。自治体や福祉団体、研究機関との連携によるパイロット展開が、早期の普及と社会実装を後押しすると考えられます。
参考:ノウタス プレスリリース(詳細) — PR TIMES
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
ノウタス、AIぶどう栽培の特許出願を完了し、本格展開を開始 (2025年9月21日) – エキサイトニュース
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2025-09-21-100271-43/