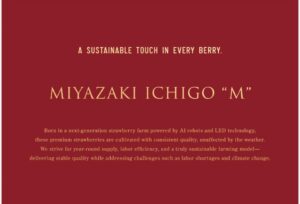旭食品グループ、ドローンで「育てる」農業へ本格参入――効率化と垂直統合が描くビジネスモデル
高知県南国市に本社を置く食品卸売業・旭食品のグループ会社、旭ドリームファームが本格的に農業へ参入しました。従来の「売る」立場から一歩踏み込み、自ら酒米やユズを栽培して仕入れ供給の安定化を図る取り組みです。高知さんさんテレビの報道によれば、ドローンを駆使した農薬散布などスマート農業技術を導入し、効率化と労働負担の軽減を実現しているとのことです。
現地の状況:2.4ヘクタールの試験圃場とドローン散布
取材によれば、旭ドリームファームは南国市で酒米を中心に2.4ヘクタールの田んぼを耕作しています。現場では人が田んぼに入らず、ドローンによる農薬散布で作業を行っており、手作業で半日かかる散布がドローンだと約30分で済むと報告されています。朝倉和也社長は「労力の削減を行って、これから農業の新規参入者が増えていくようなモデルケースを作りたい」と話しています。
「作業の様子を見ていますと畑の中には誰も入っていません。その代わりに虫の発生を防ぐための農薬をドローンがまいています」――川村和久アナウンサー(取材より)
なぜ卸売業が自分で作るのか:背景と狙い
旭食品が農業に乗り出した背景には、地域の農業者の高齢化に伴う原料調達の不安があります。加工食品の原料である農作物の安定調達を将来にわたり確保するため、農業法人を立ち上げ、耕作放棄地を借りて生産に着手しました。酒米は地元の農協やグループ企業の醸造所(酔鯨酒造)などへ供給する計画で、県内の酒米自給率向上を掲げ、将来的には100ヘクタール規模まで拡大する目標を示しています。一方、ユズは苗木からの育成で収穫まで約5年を見込んでおり、販路を海外に広げる計画もあります。
現場でのメリット:労働、時間、安全性、コストの改善
- 作業時間の大幅短縮:人手による散布が半日かかるところをドローンで約30分に短縮。
- 労働負担の軽減:重労働や田んぼへの立ち入りを減らし、高齢者や新規参入者にも優しい作業環境を実現。
- 安全性の向上:薬剤散布時の人への曝露リスクを低減。
- 効率的な労働配置:現場スタッフは水管理や生育チェックなどの観察業務に注力できる。
スマート農業の“作り方”―導入技術と運用上のポイント
報道ではドローン散布が中心ですが、スマート農業の本格的な運用では以下のような技術や運用体制が重要になります。
- ドローン運用:散布用ドローンのペイロード、航続時間、RTK(高精度位置計測)や自動航路設定の活用が有用です。
- センシングと解析:空撮による生育モニタリング(RGBやマルチスペクトル)、NDVI等による生育診断で、散布の必要箇所を特定する変量散布(VRA)が可能です。
- データ統合:圃場ごとの生育履歴や気象データを農業管理プラットフォームで一元管理し、AIを活用した病害予測や最適散布計画に繋げると効果的です。
- 人的資源:ドローン操縦者の技能や保守点検、薬剤取扱いの教育、安全ルールの遵守が必須です。
課題とリスク管理
導入効果は大きい一方で、拡大にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 法規制・飛行ルール:飛行許可や夜間飛行、目視外飛行の許認可など、関係法令と自治体ルールの遵守。
- 気象リスク:風や降雨による散布精度低下、薬剤の拡散リスクへの対策。
- 薬剤の適正使用:薬剤散布の最適化と周辺環境への配慮(ドリフト対策、緩衝帯設定など)。
- 投資回収:機材・教育・システム導入費用と運用コストのバランス、収量向上や取引先確保による収益予測。
- サプライチェーン管理:収穫後の調製・貯蔵・物流、品質証明や輸出時の規制対応。
ビジネスモデルとしての示唆:垂直統合と地域連携
旭食品グループの取り組みは、原料の安定供給を目的とした垂直統合の典型例です。卸売業が生産側に参入することで、下請け的な調達リスクを減らし、品質やトレーサビリティをコントロールしやすくなります。今後のスケールアップに向けては、次のような展開が考えられます。
- 協力農家との協働:技術移転や共同でのスマート農機導入により地域全体の生産性向上を目指す。
- サービス提供モデル:ドローン散布やデータ解析を地域の他農家向けに受託し、新たな収益源を確保する。
- 付加価値化:酒米ブランド化や輸出を見据えた品質認証(有機、GAP等)で販売単価を引き上げる。
現場からの声と今後の展望
朝倉社長は「酒米の県内自給率を上げていきたいので100ヘクタールまでに育てて協力農家と推進していきたい」と述べています。ユズは苗木育成のため収穫まで5年を要しますが、将来的には海外販路の開拓も視野に入れており、短期の効率化だけでなく中長期の事業成長を見据えた計画です。
農業経営者・支援者への提言
旭ドリームファームの事例は、卸売・加工事業者が自らのサプライチェーンを守るために生産へ参入し、スマート農業で労働負担を下げる好例です。導入を検討する際は以下を確認してください。
- 導入目的を明確にする(労働削減、品質向上、原料確保など)。
- 現場条件に適したドローンやセンサーの仕様を選定する。
- 試験圃場で検証を行い、収量・コスト・リスクの実データを積み上げる。
- 自治体、JA、地元事業者と連携して、ヒューマンリソースや販路を強化する。
旭食品グループの挑戦は、地方の資源を活かしつつテクノロジーで生産の未来を築くモデルの一つになり得ます。スマート農業は単なる機械化ではなく、データと運用の組合せで初めて真価を発揮します。農業経営者やアグリテック関係者は、実証と協働を通じて拡張性のあるモデルを設計していくことが重要です。
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
【高知】“売る”から“育てる”へ 旭食品グループがドローン駆使し「スマート農業」へ本格参入(高知さんさんテレビ) – Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0b343232a4c291fe987388d81757e70718015a1