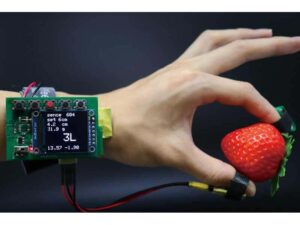AGRIST×宮崎市、土耕圃場向けきゅうり収穫ロボット実証で55%の収穫率を確認 — 課題と導入の実務知見を公開
AGRIST株式会社は宮崎市と共同で進める「きゅうり収穫ロボット導入モデル構築事業」に関する令和6年作の実証結果報告会を開催しました。本実証では、AI搭載の自動収穫ロボットを土耕圃場へ導入した際の可能性と課題を洗い出し、将来的な普及に向けた実践的な知見を得ることを目的としています。今回の実証でロボットは土耕栽培の条件下で55%の収穫率を達成し、初期モデルからの性能向上が確認されました。一方で葉が繁茂した際の視認性低下が収穫率低下の主要因として明確になり、今後の改良の最重要課題と位置づけられています。
実証の概要と主な成果
- 実証栽培:土耕圃場(トンネル・ハウス想定)における令和6年作
- 収穫率:ロボット単体で55%を達成(初期モデルから大幅改善)
- 得られた実務知見:通路幅やハウス内高さの最適値、レール設置・資材搬入撤去にかかる工数など
今回の55%という数値は、ロボットの自動収穫能力が実用化に向けて一定のポテンシャルを持つことを示しています。ただし、実用的な導入やコスト回収を考えたときには収穫率のさらなる向上が必要です。特に葉の繁茂による視認性低下は、作付けや栽培管理、ロボット側の認識アルゴリズム双方での対策が不可欠です。
実務的に明らかになった導入要件
実証を通じて、導入に関する「現場で使える」知見が多く得られました。主なポイントは次のとおりです。
- 通路幅・ハウス高さ:ロボットが安全かつ効率的に稼働するための最小寸法が判明しました。現場ごとのハウス規格に合わせた改修の必要性が出てきます。
- レール設置の負担:レールを敷設する場合の作業手順や資材の搬入・撤去にかかる工数が可視化され、導入前の現場調査と工程計画の重要性が確認されました。
- 運用フロー:ロボット稼働中の人手の役割(畝間移動の支援や補助作業)や保守・点検体制をどう組むかが導入の成否を左右します。
明確になった技術課題:葉の繁茂による視認性低下
最大の課題は、きゅうりの葉が繁って果実が隠れてしまうときに発生する視認性低下です。視認できない果実は収穫対象として検出できず、収穫率が低下します。これに対しては複合的なアプローチが必要です。
- 栽培側の対策:植え付け密度の調整、定期的な葉かきや誘引方法の見直し、果実が見えやすい栽培体系(高軒高ハウスや支柱・テープの配置)など。
- ロボット側の技術改良:画像処理・AIの高性能化、マルチビューカメラや深度センサーの導入、葉越しでも果実を推定する認識ルールの高度化。
- 運用面の工夫:収穫タイミングの最適化(葉が比較的少ない時期に重点的に稼働)や人手とロボットを組み合わせたハイブリッド運用。
改良計画と今後のロードマップ
AGRISTは以下のスケジュールで改良を実装し、次期モデルへ反映する計画です。
- 2025年1月頃:現行モデルへの改良実装(SNSアプリを使った通知機能強化、アーム動作改善、ハサミのエラー低減など)
- 2025年10月以降:作物認識ルール変更やアーム動作のさらなる改善を実施し、2025年10月末リリース予定の次期モデルに反映
とくに視認性向上のための認識アルゴリズム改良は最優先で取り組まれており、持続可能な農業実現に向けた開発が加速しています。
自動収穫ロボットの主な仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 重量 | 60 kg |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 1,110 mm × 760 mm × 1,520 mm |
| 連続稼働時間 | 10時間(畝間移動は手動) |
| 収穫能力 | 0.3 本/分(仕様値) |
| 主な機能 | 収穫サイズ設定、スマートフォン通知、過負荷検知による安全停止 |
導入を検討する現場への提言
中小〜大規模の経営者や営農支援担当者に向けて、現場での導入検討に当たって押さえておくべき実務的ポイントをまとめます。
- 現地調査を入念に行う:ハウスの高さ、通路幅、搬入口や作業動線、電源や通信環境を事前に確認してください。
- 試験導入から始める:まずは限定区画でのトライアルを実施し、収穫率・稼働率・保守コストなどを実データで評価してください。
- 栽培方法の最適化とセットで考える:ロボット前提の栽培設計(誘引・葉かき・植え付け計画)を検討すると効率が高まります。
- 運用ルールと人材育成:ロボットの保守・緊急対応や、ロボットと人手が協働する作業フローを整備してください。
- データ活用の計画を作る:収穫ログや故障履歴を蓄積し、改善サイクルに活用する体制を整えてください。
示唆と今後の展望
今回の実証は「ロボットが土耕圃場でも一定の成果を出せる」ことを示した一方で、現場改修や栽培管理、認識精度の向上といった複数の要素がそろって初めて実運用に耐えうることを示しました。特に国内の人手不足や高齢化を背景に、こうした技術は長期的に重要性を増していきます。今後はAGRISTの改良計画がどれだけ現場の多様性に対応できるか、また自治体やJA、メーカー、営農コンサルタントとの連携で導入コストや現場負担をどう軽減できるかが普及の鍵になります。
導入を検討する農業経営者や自治体、メーカーの技術担当者には、現場でのトライアル参加やデータ共有による共同改善を強くお勧めします。現場の声を反映した改良こそが、実運用での成功と持続可能な普及につながります。
AGRISTと宮崎市の取り組みは、現場に即した知見を提供する良いモデルケースです。今後のモデル改良と次期モデルのリリースにより、収穫率・稼働率ともに改善が進めば、実際の導入がぐっと現実的になります。現場側は今回の知見を活用し、栽培設計や作業動線の見直し、試験導入計画の策定を進めていただくとよいでしょう。
詳しい記事の内容はこちらから(引用元)
AGRIST×宮崎市「きゅうり収穫ロボット導入モデル構築事業」進捗 – ロボスタ
https://robotstart.info/2025/09/09/agrist-miyazaki.html